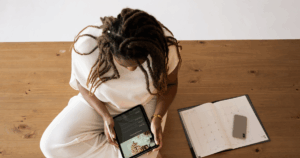在留資格「永住者」に必要な提出書類は、どこで何を集めますか?
とにかく永住資格を申請するにあたっては、行政書士に依頼する前に必ず法務省の「永住許可申請チェックシート」で永住申請して合格できるのかどうか、最初にチェックしてください。ここで「いいえ」が多い場合は永住が認められる可能性が低いということになりますし、その分の行政書士への依頼費がも無駄になる可能性が高くなります。なお、噂のレベルではありますが、独身者が永住するのは年収300万円、配偶者がいる場合には1人当たり60万円から80万円が必要と言われていますので、その計算も考慮に入れてください。例えば、妻と子供二人がいる外国人の場合、独身時の300万円に加えて180万円から240万円、つまり年収が480万円から540万円程度ないと永住申請を拒否される傾向にあります。
行政書士の永住申請費用が経営者とそれ以外で価格が異なるケースが多いですが、これは経営者の方が必要書類が多く手間がかかることに起因します。以下に用意すべき書類を書いてゆきます。
①市町村役場で取得する書類
税金関係とそれ以外に分けて説明いたします。
(1)住民税関係
- 同居の家族分を含めて住民税の課税証明書(課税です)
- 同居の家族分を含めて住民税の納税証明書(納税です)
- 同居の家族分を含めて国民健康保険税の納税証明書→会社で社会保険に加盟している場合や、社会保険に加入している方の不要に入っている場合は不要です。
(2)住民票や戸籍の関係
- 世帯全員分で省略のない住民票(住民コードと個人番号を除く)
- 配偶者や親が日本人の場合、戸籍謄本→本籍地の役所なのでご注意ください
- 本人が日本で生まれている場合、出生届の記載事項証明書
- 日本の役所に婚姻届けを提出している場合、婚姻届の記載事項証明書
②税務署で取得する書類
税務署で取得する書類は、照明を受けようとする各税目について申請日時点で未納がないことを証明するために必要となります。そのために対象期間の指定は不要となります。
- 源泉所得税及び復興特別所得税
- 申告所得税及び復興特別所得税
- 消費税及び地方消費税
- 相続税
- 贈与税
➂年金事務所で取得する書類
年金事務所で取得する書類で注意するのは基礎年金番号を黒塗りして復元できない状態にする必要がありますので、できれば行政書士にご依頼なさるのをお勧めします。
- ねんきん定期便→全期間の年金記録情報が表示されているものが必要です。毎年年金機構で送ってくれるハガキは全期間になっていないのでこれを使用することはできません。ただし、この書類を申請してから交付するまでに約2か月かかるので、ねんきんネットの「各月の年金記録」で代用することをお勧めします。日本年金機構のホームページから登録すると1週間ほどで自宅にユーザーIDが送られてくるので、それを使用して「各月の年金記録」を見られるようになりますので、これを提出書類とする方が迅速です。
- 申請する方が社会保険適用事務所の事業主である場合、社会保険料納入証明書→直近2年分(高度人材ポイント80点以上の方は直近1年分)の期間を記載して一括用及び明細・遅延金を含む形で取得してください。
- 被保険者記録照会(納付Ⅰと納付Ⅱ)→下の⑥の自分でコピーして集める書類のうち、「国民健康保険税の領収書」を紛失している場合のみ。
④法務局で取得する書類
法務局で取得する書類は、不動産を所有しているなら不動産に関する書類、法人の経営者(同居者の誰かが経営者であるときを含むので注意)の2つのケースになります。両方とも該当しないなら法務局で取得する資料はないということになります。不動産に関しては所有目的を問いませんので、住居目的であろうと投機目的所有であろうと同居の家族の所有している不動産をすべて含めて下さい。同様に法人経営者の場合も、同居人に経営者がいる場合は法務局で取得すべき書類が増えるので注意が必要です。
- 建物の登記事項証明書
- 土地の登記事項証明書
- 法人の登記事項証明書
⑤会社で取得する書類
一番望ましいのは、会社から毎月もらっている書類をためておくことですが、失くしてしまっていたり捨ててしまっている場合は、会社から給与証明書を発行してもらうようにしてください。書類の期間が異なるので、注意してください。
- 源泉徴収票(原本)→直近の5年または3年。
- 在職証明書(3か月以内のもの)
- 給与明細書(直近3か月)
⑥コピーして用意する書類
結構面倒な作業ですが、保険者番号、被保険者等の記号・番号は黒塗りにするなどして復元できない状態にしてから提出する必要があります。
- 健康保険証
- 国民健康保険税の領収書等→会社員の場合は不要です。もし失くしてしまっていたら、年金事務所で被保険者記録照会(納付Ⅰと納付Ⅱ)を取得することによって代用が可能です。
- 健康保険、厚生年金保険料領収書→申請する方が社会保険料適用事業所の事業主である場合に必要となります。
- 預金通帳→国民健康保険税や国民年金、社会保険料等を口座振替で利用している方は該当ページをコピーしてください。
- 住民税の領収書→住民税を普通徴収で知ら頼をしている場合に必要となります。サラリーマンなら会社の給料から天引きですが、フリーランスや会社経営者等自身で支払っている場合は、必要書類になります。
⑦身元保証人に用紙してもらう書類
この場合は身元保証人が会社員か経営者かで異なります。
(1)会社員の場合
- 身元保証書
- 在職証明書
- 住民税の課税証明書(直近1年分)
- 住民税の納税証明書(直近1年分)
- 住民票(世帯全員分必要、ただし住民コードと個人番号は除く)
(2)会社経営者の場合
- 身元保証書
- 法人登記事項証明書
- 住民税の課税証明書(直近1年分)
- 住民税の納税証明書(直近1年分)
- 住民票(世帯全員分必要、ただし住民コードと個人番号は除く)
⑧本国から取得する書類
中国人でしたら、中国の「公証処」で出生公証書、婚姻公証書、家族関係証明書を取得する必要があります。それぞれの国で異なるので、母国の行政機関に問い合わせるのが一番早いです。私は行政書士ですが、外国の法改正までは即時対応できないことでお客さまに迷惑をかけることができないので毎回必ず大使館等に確認をすることにしております。私としましては、行政書士や弁護士等の専門家に依頼する方が効率が良いと思います。
⑨申請時に必ず持参すべき書類
意外とどこの入管に持っていくのかわからない時があります。入管には管轄があるので、必ず前もって調べることをお勧めします。
- 収集した書類一式
- 作成した書類一式
- 在留カードの原本
- パスポートの原本
最初の2つは①から⑧までなので大丈夫だと思いますが、パスポートの原本は意外と盲点なのでご注意下さい。
⑩申請後について…必ず読んでください!
収集した書類、作成した書類等のすべての資料を持参して出入国在留管理庁に行き、無事に申請受付となった場合は、遅滞なく審査が開始されます。公表されている標準審査期間は4か月ですが、実際には6か月前後かかることもあります。審査の途中で入管で確認したい事項や情報が足りない場合や追加資料提出要求をされる場合があります。この時は誠実に対応してください。入管からの連絡があれば、丁寧かつ適切に対応することを心掛けて下さい。
また審査中ですので極力審査時の提出資料が真実である状態を保ってください。時々転職をしてしまう外国人がいらっしゃいますが、提出書類の内容と異なるため、審査が長くなり、最悪のケースでは入管の心証が悪くなるので要注意です。